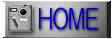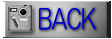人 吉 城 

|
||
| 別 名 | : | 相良城・三ケ月城・繊月城・涅槃城 |
| 所在地 | : | 熊本県人吉市麓町 |
| 築城年月 | : | 建久9年(1198年) |
| 築城者 | : | 相良長頼 |
| 主要城主 | : | 相良氏 |
| 城郭様式 | : | 平山城 |
| 遺 構 | : | 石垣・門跡 |
| 人吉城はもともと平氏の代官がいた城でした
鎌倉時代のはじめ、源頼朝の命を受け人吉庄の地頭として着任した遠江国相良庄を出身とする相良長頼によって修築された 人吉城が石垣造りの近世城として整備されるのは天正17年(1589)20代長毎のときからです 何度も中断しながら51年後の寛永16年(1639年)に現在の形になっています
|
 |
 | |
| 隅櫓です。人吉城北西隅の要所に建てられた櫓です。間口22m×奥行7m、瓦葺、入母屋造りで壁は上部漆喰塗り下部が板壁となっている | 隅櫓古写真です |
 |
 | |
| 大手門横長櫓です。大手門の脇を固めるために造られた長屋型の櫓である | 大手門横長櫓古写真です |
 |
 | |
| 大手門跡です。胸川御門とも呼ばれ石垣の上に櫓をわたして下に門を設けてあった。門前の通路は鍵形にして枡形に作り、門の北側には多聞櫓を建て門内には番所を置いて監視していた | 武者返しの石垣です |
 |
 | |
| 間米蔵跡です。水の手門周辺には大村米蔵、欠米米蔵、間米蔵の3棟あった | 水の手門跡です。城内に入る4ヶ所の門のひとつで球磨川に面する水運のための門であったことからこの名がついた |
 |
 | |
| 堀合門です。城主が住む御館の北側にあった裏門です | 大村米御蔵跡・欠米蔵跡です |
 |
 | |
| 御下門跡です。下の御門とも呼ばれ人吉城の中心である本丸・二の丸・三の丸への唯一の登城口に置かれた門です | 三の丸虎口です |
 |
 | |
| 中の御門跡です | 二の丸石垣です |
 |
 | |
| 本丸土塁です | 本丸護摩堂礎石です |
 |
 | |
| 埋門跡です | 御館石垣です |
 |
 | |
| 御館御門跡です | 力石です |
 |
 | |
| 居石です | 後口馬場の井戸跡です |
 |
 | |
| 岩下門跡です。城内に入る4ヶ所の門のうち南側入口にあった門です | 谷口舟渡跡ですです |
 |
 | |
| 地蔵院跡です | 堀合門(武家蔵)です。現存する唯一の門です |
 |
 | |
| 城址碑です | 全景です |