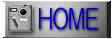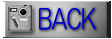八 代 城 

|
||
| 別 名 | : | 白鷺城・不夜城 松江城・不知火城 |
| 所在地 | : | 熊本県八代市松江城町 |
| 築城年月 | : | 元和8年(1622年) |
| 築城者 | : | 加藤正方 |
| 主要城主 | : | 加藤氏・松井氏 |
| 城郭様式 | : | 平城 |
| 遺 構 | : | 空堀・石垣・水堀 |
| 元和5年(1615年)肥後一帯を襲った大地震のため麦島城が崩壊し甚大な被害を受けたので加藤忠広は麦島城を廃城にして新城築城の許可を受け、加藤正方に築城を命じ元和8年(1622年)に完成した
寛永9年(1632年)加藤忠広が改易となり小倉から細川忠利が熊本城に入ったため、忠利の父細川忠興が八代城に入り、北の丸を隠居所として本丸には4男立孝を入れた 正保2年(1645年)藩主光尚は重臣長岡佐渡興長を八代城主とし、明治3年(1870年)の廃城まで松井氏が城主となった
|
 |
 | |
| 舞台脇櫓跡です。梁間四間、桁行九間の建物で再建後は十二間櫓とも呼ばれている。東側の宝形櫓との間には梁間三間、桁行三十間の三十間櫓と呼ばれる平櫓があった | 宝形櫓跡です。方形櫓ともいい一階は四間四方、二階は三間四方の大きさの二階建て櫓であった |
 |
 | |
| 磨櫓跡です。高麗門の南側にあり東西4間、南北7間の平櫓です。南側の宝形櫓との間には長さ16間の塀が続いていた | 高麗門跡です。高麗門は欄干橋門とも呼ばれ八代城本丸の正門に当たる表枡形門の一の門です。枡形門は四方を石垣で囲み2箇所に門を設けたもので高麗門を通り抜け鍵の手に曲がった所に二の門である頬当て門があった |
 |
 | |
| 埋門跡です。本丸から北の丸は通じる裏枡形門の二の門です。両側の石垣の上に梁間2間半、桁行5間の平櫓を渡しその下部に幅3間半の門を設けてあった | 廊下橋門跡です。本丸の裏門にあたる裏枡形門の一の門です。両側の石垣の間に東西5間、南北2間半の平櫓を渡しその下部に門を設けてあった |
 |
 | |
| 小天守台です | 小天守閣跡です。東西9間、南北4間半の地階付2層3階の天守閣です。大天守閣とは東西4間、南北8間の渡り櫓で結ばれており、天守閣の下の平場から石段を通って小天守閣の地階に入り渡り櫓から大天守閣の地階へと入った |
 |
 | |
| 天守台です | 大天守閣跡です。東西10間、南北11間の地階付5層6階の建物であった |
 |
 | |
| 月見櫓跡と水堀です。本丸の南西隅にある二階建ての櫓です | 城址碑です |
 |
 | |
| 北の丸松井神社の石垣と水堀です | 北の丸松井神社の石垣です |