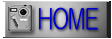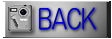京 都 御 所 

|
||
| 別 名 | : | 土御門東洞院殿 |
| 所在地 | : | 京都府京都市上京区 |
| 築城年月 | : | 不明 |
| 築城者 | : | 不明 |
| 主要城主 | : | 天皇 |
| 城郭様式 | : | 皇居 |
| 遺 構 | : | 空堀 |
| 平安から鎌倉時代には土御門東洞院殿と呼ばれる里内裏のひとつであった
元弘元年(1331年)北朝の光厳天皇が皇居と定めた
|
 |
 |
|
| 御車寄です。昇殿を許された者が正式に参内する時の玄関です | 諸大夫の間です。正式に参内した者の控の間で身分に応じて異なる部屋に控えた。最も格の高い公卿の間(虎の間)、諸侯・所司代の殿上人の間(鶴の間、それ以外の諸大丈の間(桜の間)がある |
 |
 |
|
| 新御車寄です。大正4年(1915年)大正天皇の即位礼に際して天皇皇后両陛下のための玄関として建てられた | 紫宸殿です。即位礼などの重要な儀式を執り行なう最も格式が高い正殿です。大正天皇・昭和天皇の即位礼もここで行われた |
 |
 |
|
| 月華門です | 建礼門です |
 |
 |
|
| 承明門です | 日華門です |
 |
 |
|
| 春輿殿です。大正4年(1915年)大正天皇の即位礼に際し神鏡を奉安するために建てられた | 宜陽殿です |
 |
 |
|
| 清涼殿です。天皇の日常生活の場として使われた御殿です | 小御所です。皇太子の元服などの儀式に用いられ将軍や諸侯の対面の場として使われた。慶応3年(1867年)王政復古の大号令が発せられた夜「小御所会議」がここで行われた |
 |
 |
|
| 蹴鞠の庭と御学問所です | 御池庭です。よくTVで見るアングルです |
 |
 |
|
| 御学問所です。親王宣下や御進講、月次の和歌の会などに使われた | 御常御殿です。室町時代以降天皇の日常の生活の場として使われた御殿です |
 |
 |
|
| 御三間です。七夕や盂蘭盆会などの内向きの行事に使われた | 清所門です |
 |
 |
|
| 宜秋門です | 乾御門です |
 |
 |
|
| 中立売御門です | 蛤御門です。元冶元年(1864年)長州藩と会津・薩摩藩が戦った禁門の変で有名である |
 |
 |
|
| 瑞雲文様赤地錦で金色の太陽が刺繍された日像纛旛と瑞雲文様白地錦で銀色の月が刺繍された月像纛旛です。昭和天皇の即位式に使用された | 蹴鞠です |
 |
 |
|
| 帽額です。即位式の折紫宸殿南面の長押上に掛ける幕で大正天皇と昭和天皇の即位式に使用された | 帽額使用写真です |
 |
 |
|
| 威儀物です。即位式にあたって儀式の威儀を整えるための物で太刀、弓、箭、桙、楯をいう | 紫宸殿の内待臨東檻です。内侍(女官)は紫宸殿の簀子上の南東角にて親王、公卿等に昇殿するように檜扇をかざして合図します |
 |
 |
|
| 紫宸殿の右側にあるのが御帳台で皇后の御座として用いられる。中央にあるのが高御座で即位の儀式に天皇の御座として用いられる | 紫宸殿の西階進御膳です。節会の時は御膳具が準備されここから采女と呼ばれる女官が紫宸殿の母屋へ御膳を運びます |
 |
 |
|
| 軟障(ぜじょう)です。白精好地の千年松を墨画し縁は紫色小葵文様の錦をめぐらした幔幕 | 皇后宮常御殿です。女御あるいは皇后が日常お住まいとして使用された御殿で内部は13室からなる |
 |
 |
|
| 玄輝門です | 朔平門です |
 |
 |
|
| 飛香舎(藤壺)です。平安京内裏の様式を伝えている桧皮葦寝殿造りの建物です。女御入内の儀式が執り行われる建物であるが元来は女御が日常過ごしていた所で中庭に植えられていた藤にちなんで藤壺とも呼ばれた | 若宮・姫宮御殿です。皇子・皇女のお住まい御殿です |