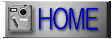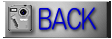丸 岡 城 

|
||
| 別 名 | : | 霧ヶ城 |
| 所在地 | : | 福井県坂井郡丸岡町 |
| 築城年月 | : | 天正4年(1576年) |
| 築城者 | : | 柴田勝豊 |
| 主要城主 | : | 柴田氏・有馬氏 |
| 城郭様式 | : | 平城 |
| 遺 構 | : | 天守閣 |
| 丸岡城は天正3年(1575年)織田信長より越前の領主に封ぜられた柴田勝家が本城北の庄城に対する北方の支城として甥の柴田勝豊に築かせたものである
天正10年(1582年)勝豊は長浜城に移り勝家の臣守井家清が丸岡城代になった 天正11年(1583年)柴田勝家が豊臣秀吉と戦い北ノ庄城を攻められ滅亡すると丹羽長秀が北ノ庄城に入り丸岡にはその臣青山宗勝が入城した その後徳川家康の次男結城秀康が越前を領有しその臣今村盛次が城番として入ったが慶長17年越前騒動により所領が没収され翌年本多成重が入封、4代続いたが元禄8年(1695年)丸岡騒動で没収され有馬清純が入封し代々世襲し明治に至った 天守台上の建物入口に石の階段を登るのは珍しい構造であり、また屋根瓦が寒冷破損を防ぐためすべて石造りとなっている 現存する天守閣の中で最も古い建築で天守は回縁をめぐらせた望楼を櫓の上に載せた形態で前期望楼型の典型とされている また1階の母屋柱は掘立柱で2・3階まで柱が通じていない古い構造となっている
|
 |
 | |
| 天守閣です | 階段です。なんとロープが張ってありました。急でしたよ |
 |
 | |
| 門跡です | 人柱お静の供養塔です。いわれはこぼれ話を読んで下さい |
 |
 | |
| 井戸です。柴田勝豊が豊原からこの地に移り築城したが、豊原は一向一揆の最後の根拠地であったためこの地に築城後も一揆の残党が攻撃をしかけてきたが、そのたびにこの井戸から大蛇があらわれ城に霞をかけて城の危機を救った。この伝説が別名「霞ヶ城」と呼ばれる由来である。現在も春先にすっぽりと霞に覆われた霞ヶ城を見ることが出来る | 石製鯱です。この鯱はもと木彫銅板張りであったものを昭和15年の修理時戦争で銅板が入手困難であったため天守閣の石瓦と同質の石材で作り変えたがこの石製の鯱も昭和23年6月の福井大震災により棟より落下し現在の様な形で残っている。現在天守閣の上にのっている鯱はもとの木彫鋼板張りに復元したものである |
 |
 | |
| 牛ヶ島石棺です | 絵図です |