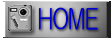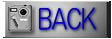郡 上 八 幡 城 

|
||
| 別 名 | : | 積翠城 |
| 所在地 | : | 岐阜県郡上市八幡町 |
| 築城年月 | : | 永録2年(1559年) |
| 築城者 | : | 遠藤盛数 |
| 主要城主 | : | 遠藤氏・青山氏 |
| 城郭様式 | : | 山城 |
| 遺 構 | : | 石垣 |
| 承久2年(1220年)下総国(千葉県)香取東の庄千葉氏の支流東胤頼が山田の庄を賜り郡上東家の初代となり、応永16年7代益之のとき赤谷山に城を築いた
応仁2年(1468年)9代城主常縁は東征の留守の間に土岐家の守護代斎藤妙椿に篠脇城(大和村牧)と所領を奪われたが、常縁の読んだ和歌に心を動かされた妙椿は所領を返した 天文年間(1532〜1554年)13代常慶は東殿山城(八幡町旭)を築いた 永録2年(1559年)常尭は支城木越城(大和村場皿)城主遠藤胤縁の娘との縁組を申し込んだところ拒まれたのを恨み陰謀をもちい胤縁を殺害した 永録2年(1559年)8月24日苅安林広院山城主遠藤六郎左衛門盛数は兄胤縁の弔い合戦の名目で東殿山の常慶を攻撃して滅ぼし、八幡山に城を築いたこれが現在の八幡城である これで承久以来12代340年も続いた東氏は滅び、盛数は郡上一円を領し胤縁の子胤基に木越城を継がせ所領の半分を分け与えた 永録7年(1554年)春盛数の子で2代目慶隆が井之口(岐阜市)に滞在中胤基は不意を襲って八幡城を奪い慶隆とその弟慶胤へ叛旗をひるがえしたが、急を知った慶隆は関城主長井道利(慶隆の母の再縁先)の助けで八幡城を奪い返し、敗軍の将となった胤基は木越城をその子胤直に譲り剃髪し出家した 天正16年(1588年)慶隆は岐阜城主織田信孝に通じていたので豊臣秀吉に疎まれ2万石を没収され加茂郡小原犬地に転封され、八幡城には安八郡曽根から稲葉一鉄の子稲葉右京亮貞通が4万石で移封となり城郭を修築し天守台等を設けた 慶長5年(1600年)慶隆は家康に願い出て飛騨の金森可重の援軍を受け9月1日八幡城の稲葉通孝を攻めるため可重は小野山に陣取り慶隆は大宮山王(八幡町日吉神社)に陣を構え両面から城を攻撃し2日通孝から和睦の申し出があって慶隆は大宮の陣をとき愛宕山の本陣へ兵をひいた そのころ犬山城にあった稲葉貞通は八幡城が包囲されたとの報を受け、急遽兵をまとめ3日愛宕山本陣の慶隆を奇襲し慶隆は小野山の可重の陣に危く逃れ貞通は凱旋をあげて八幡城にはいった 慶隆、可重の軍は小野山から八幡城を攻め搦手で激戦の末和睦した 稲葉貞通は関が原の戦いで西軍に属して出陣したため豊後国(大分県)臼杵へ5万石で移され、替わって慶隆が二万七千石で再封し8年には松の丸・桜の丸を築いた 元禄5年(1692年)5代目城主常久は7歳で死亡し後嗣がなく廃絶となり常陸国笠間城主井上中務少輔正任が5万石で城主となった 元禄10年(1697年)2代城主井上正任の子正岑は丹波国(京都府)亀山に移され、羽州(山形県)上の山から元高山城主金森出雲守よりときが3万8千石で城主となった 元文元年(1736年)よりときが死に嫡孫の頼錦が2代目城主を継いだが、晩年幕府の奉者役という重職から出費が多くなり年貢増徴の苦肉の策から宝暦4年(1754年)領内の農民の一揆(宝暦騒動)が起き、頼錦は世怠惰の責任を問われ金森家は断絶となり丹後国(京都府)宮津の城主青山大和守大膳亮幸道が国替となり八幡城主となった 宝暦9年(1759年)3月美濃国岩村城主松平能登守乗薀が留守居城主を命ぜられた 宝暦9年(1759年)6月青山幸道が八幡城主に赴任して4万8千石の新しい統事者となり、以後青山氏は郡上藩の領主として7代111年年間続き明治2年(1869年)青山幸宜が藩籍を朝廷に返し郡上藩知事となった
|
 |
 |
|
| 模擬天守です | 隅櫓と石垣です |
 |
 |
|
| 隅櫓です | 首洗い井戸跡 この浅井戸は慶長の合戦に際して討ち取られた寄せ手の名ある武士の血や泥で汚れた首が洗い浄められ首実験に供されたという |
 |
 |
|
| およしの碑です | 土霊水 天正16年(1588年)稲葉貞通が遠藤氏に代わって領有したのち城郭を大改修してこの地に本丸を構えこの門内にあたるここに井戸を掘った |
 |
 |
|
| 山内一豊と妻の像です | 力 石 この二つの石は寛文7年(1667年)城主遠藤常友が城を修理するため領内から多数の人夫を集めた時その中の一人である大和町の作兵衛(通称赤髭)が城下の河原からこの地まで運び上げたものである。(重さ350キロ、長さ1m、厚さ30cm)奉行の村上貞右衛門がその力量のすぐれているのを見て激賞すると彼は感涙し、たちまちその場で卒倒し息絶えてしまった。奉行は哀れに思いこの石の使用を禁じたが昭和8年天守閣を建設する際この石が草の中に捨てられていたのこの地に碑として安置した |
 |
 |
|
| 二の郭です。関が原の戦いではこの二の郭に一の門を突破した遠藤慶隆隊と桜町方面から攻め登った金森可重隊が東木戸から破ってなだれこんだためしばらく同志討ちが起こり、やがて両者は連合して二の門を突き進み二の丸の攻撃を始めたという | 凌霜隊の顕彰碑です。明治元年に行われた会津の戊辰の戦いで徳川譜代の青山藩は尊皇と佐幕の両派に分かれ江戸では凌霜隊を組織して朝比奈茂吉を先頭に鶴ヶ城では西出丸の防御を担当したが落城し故郷の元に帰されたが脱藩兵として赤谷の揚屋に押し込められたがここは湿気がひどく粗食のため病人が続出。その後城下の寺院に移され釈放されたが世間の目は冷たく隊員は故郷を捨てて他に移住した |
 |
 |
|
| 八幡屋敷跡です | 大手門跡です。この四辻は昔侍町四辻といわれ明治維新まで黒塗の立派な大手門が建っていた |
 |
 |
|
| 八幡城主御下御殿跡です | およし観音堂です |