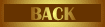|
「激戦地」 桶狭間の戦い。永禄3年(1560年)5月19日織田信長はわずかな2千騎で2万5千の今川勢を襲撃 今川義元を奇襲により破り天下統一への一歩を踏み出した有名な戦いである 桶狭間の戦いはここと豊明市の2箇所あります。近くを流れる鞍流瀬川から碑が見つかり、正面には「桶狭間古戦場」、裏面は文化13年丙子5月建」とありこちらが激戦の中心地であったのではないかとの説も出ています 「桶狭間」は「桶廻間」とも書き、旧刈谷街道であったこの地に泉が湧いており、水汲み用の桶が入れてあり、涌き出る水勢で桶がクルクル廻り、桶回る間の一服ともてはやされ、桶廻間(おけまわるま)が桶狭間と呼ぶようになったとも言われている 今川義元公水汲みの泉。別名今川義元公首洗いの泉とも呼ばれている。今川軍の本陣が田楽坪に置かれ義元が休憩の折りこの泉の水を汲み暑さをしのいだと言われている。また、義元が討死そ、首級がこの泉で清められたとも言われている 本陣跡・馬繋ぎのねずみ塚。この馬繋ぎのねずみ塚付近が本陣跡であり、義元終焉の地と伝えられており、義元の愛馬を繋いだねずの枯木が残っている。この当たりは桶狭間の原頭で無念の最期を遂げた義元の亡霊が氏蛍となって西方(京都)に向かって飛ぶとか、このねずの木に触れると熱病にかかるとの伝説がある 供養杉。長福寺の境内の大杉付近で林阿弥が首検証に命ぜられ後供養した所 戦評の松。今川方の将瀬名伊予守氏俊がこの松の根元に部将を集め戦いの評議をしたといわれている 瀬名氏俊陣地跡。今川の先発瀬名氏俊が大府、大高、鳴海方面の織田軍に備え陣地を構えていた所である |
 |
 |
 | ||
| 【義元水汲みの泉】 | 【本陣跡・馬繋ぎのねずみ塚】 | 【戦死之地碑】 |
 |
 |
 | ||
| 【供養杉】 | 【戦評の松】 | 【瀬名氏俊陣地跡】 |