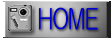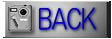| 岐阜城麓(千畳敷・居館跡) |
|---|---|
 | 岐阜城の砦 |
 | 祟福寺 |
 | 円徳寺 |
 | 信長神社 |
 | 周辺史跡 |
千 畳 敷 ・ 居 館 跡
 |
 |
|
| 冠木門です。ここから居館跡・千畳敷へと進みます | 掘立柱建物跡です |
 |
 |
|
| 石垣です | 下層遺構群です。東西及び南北方向の2列の石垣によって区画され東西方向の石垣の北に用途不明の長方形の石積施設、南北方向の南に山側に上る階段状遺構がある。通路建設時に埋められているので信長公入城以前といわれている |
 |
 |
|
| クランク状に折れ曲がる入角(いりずみ)と出角(でずみ)です。最下段の大きい石が発掘調査で出土した石垣遺構で他の小さな石は今回積んだものである | 下層石積です。信長公入城以前のもので高さ2mのうち1mが展示されている |
 |
 |
|
| クランク状に折れ曲がる入角(いりずみ)と出角(でずみ)です。最下段の大きい石が発掘調査で出土した石垣遺構で他の小さな石は今回積んだものである | 通路・階段です。土塁状遺構の東側を通りクランク状の平面形をもった入口部分(虎口)を構成する。西方から入り北へ折れて緩やかに上った後再び東へ折れこの先は川原石と山石を混用した三段の階段となり水路西側の平地に至る |
 |
 |
|
| 織田信長居館跡の碑です | 居館跡にある井戸です。石積みの基礎に松の角材4本が井桁に組み合わされ井戸底にサワラとヒノキで作られた桶が埋まっており当時はこの桶に水が溜められていたと思われる |
 |
 |
|
| 信長公の像です | 御手洗池です。昔後の山に伊奈波神社がありこの池で手を洗って参拝したことからこの名がある。長良川から取水され岐阜城の内濠・外濠につながる濠の名残とも考えられている。関ヶ原の戦いの時岐阜城が落城し城内にいた多くの女中が逃れられない運命を知り城の断崖下にあるこの池に身を投じたと言われている |
 |
 |
|
| 信長像です | 門です |
岐 阜 城 の 砦
 |
 |
|
| 権現山砦です。白山権現社があり中腹には寺があり時鐘が鳴ります | 丸山砦です。旧伊奈波神社が砦です |
祟 福 寺
 |
 |
|
| 祟福寺です | 稲場一鉄寄贈の梵鐘です |
 |
 |
|
| 血天井です。岐阜城落城時城主秀信は高野山に落ちのびたが38名の城兵は戦死し菩提を弔うためその時の血痕の付着した床板を天井に張りめぐらせたものである | 信長公愛用櫓時計です |
 |
 |
|
| 清洲城天主閣鯱です | 信長公画像です |
 |
 |
|
| 側室小倉なべ消息です。信長・信忠が本能寺で明智光秀に討たれ側室小倉氏が密かに信長公の首級を祟福寺に葬ったとのことである | 開山独秀禅師自賛頂像です。61才までここ祟福寺に住み後に甲斐武田信玄に紹請され恵林寺において「心頭滅却すれば火自ずから涼し」という有名な句をとなえ山門において信忠に焼き殺された名僧です |
 |
 |
|
| 斎藤長弘(利安)一族の宝筺印塔です。この地はもともと長弘の長良館であったが守護土岐成頼と家臣長弘が同じ夜夢の中で「この地に寺を建てるように」というお告げを聞き長弘が寄進した | 関白一条兼良寄贈の中門・土塀です。斎藤妙椿は一条兼良が美濃に下向する度歓待しその子利国は一条家と密着し兼良の娘を室とする。この室が後の利貞尼でありこの寺域のかなりの部分を寄進している |
 |
 |
|
| 織田信長・信忠父子の廟所です。祟福寺本堂の裏側にあり墓標の高さは139cm、幅39cm、厚さ30cmで位牌形の石碑で縦に両分して父子の法名が左右に並べて刻んである | 織田信長・信忠父子の位牌堂です。墓地の右側にあり土壇の上に4m四方の格子塀に囲まれた宝形胴葺屋根木造彩色の小堂に父子の位牌が安置されている |
円 徳 寺
 |
 |
|
| 円徳寺です | 円徳寺本堂です |
 |
 |
|
| 織田信長公寄進の梵鐘です | 楽市楽座札です |
 |
 |
|
| 以前の織田塚です | 現在の織田塚です |
 |
||
| 円徳寺から少し離れている所にある織田塚です |
信 長 神 社
 |
 | |
| 信長神社です | 駒爪岩です |
周 辺 史 跡
 |
 |
|
| 常在寺です。斎藤氏の菩提寺です | 二階堂氏の菩提寺です |
 |
 |
|
| 伊奈羽神社です | 美江寺観音です |
 |
 |
|
| 長良川役所と附問屋です。元和5年(1619年)に尾張藩が美濃に5万石の領地があった以前からあったと言われ、寛永13年(1639年)までは対岸の早田村にあったが、川の流れが変わるのにともなってここに移った | 忠節用水です。用水路の斜面はモルタルを使わず玉石を組んで積み上げる空積玉石張で施工されている |
 BACK
BACK